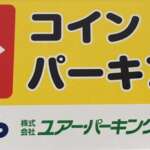- HOME
- お役立ちコラム
- コインパーキングの経営
- 駐車場経営は何坪から?台数ごとの必要面積と収益の目安を解説
土地活用として駐車場経営を検討する際にまず気になるのは「何坪必要?何坪あればできるのか」という点ではないでしょうか。
駐車場経営は、最低15㎡(約4.5坪)の土地から始めることができ、この「必要面積」は、普通自動車1台分の最小駐車マスに相当します。
ただし、この面積はあくまで法的な最低限の広さであり、利用者の快適性や効率的な収益化を考えると、より広い土地が望ましい場合もあります。
所有する土地の広さや形状、そしてどのような種類の駐車場を経営したいかによって、「何坪必要」かの考え方は大きく変わっていくのです。
本記事では、駐車場経営に必要な土地の広さや台数ごとの面積の目安などを詳しく解説します。
駐車場経営を検討中の方は、ぜひ最後までご覧ください。
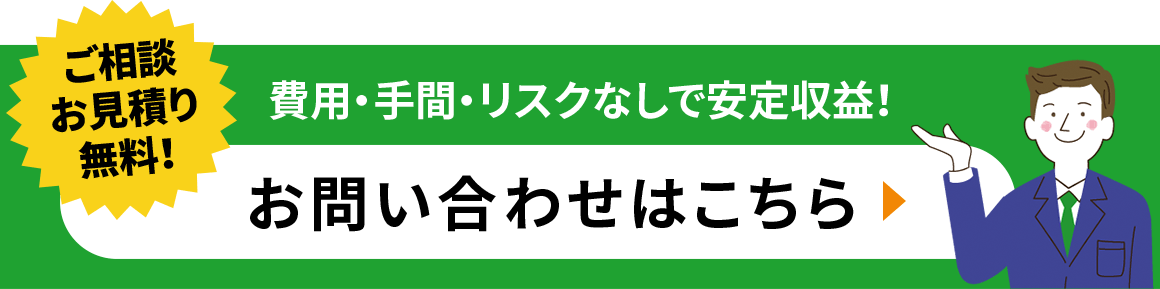
駐車場経営は何坪から始められる?
駐車場経営は、自動車1台が駐車できるスペースがあれば成立するため、最低15㎡(約4.5坪)から始めることが可能です。
これは国土交通省の指針で定められた普通自動車1台分の最小駐車マス(幅2.5m×奥行き6.0m)の面積です。
そのため、5坪に満たない土地でも、形状によっては駐車場として活用できる可能性があります。
例えば、3坪や4坪といった面積でも、軽自動車専用とすれば設置できるケースも考えられます。
1坪からでは現実的ではありませんが、狭いからと諦めずに、まずは所有する土地で1台分のスペースが確保できるかを確認することが第一歩となります。
車1台分の駐車に必要な最小面積
駐車場経営を始めるにあたり、普通自動車1台分の駐車スペースについて知っておくべきことがあります。 国土交通省の「駐車場設計・施工指針」では、普通乗用車1台分の駐車スペースとして、長さ6.0メートル×幅員2.5メートルが目安とされています。これは約4.5坪に相当する場合があります。 一般的な駐車マスの広さは約2.5m × 5.0m = 12.5㎡とされていますが、これは標準的な広さであり、法律で定められた最小限の広さではありません。駐車場法では、路外駐車場で機械式駐車装置を設置する場合など、自動車1台あたり15㎡として算定することがあります。 このように、法律で定められた最小限の広さとは異なるものの、狭小地でも駐車場経営は可能です。しかし、利用者が駐車しやすい環境や車の出入りのしやすさを考慮すると、もう少し広めの土地が望ましいとされています。
快適な乗り降りを考慮するなら1台あたり約7.5坪が理想
法律で定められた最低限のスペースは、あくまで駐車できる最低限の広さです。
利用者がストレスなく車のドアを開閉し、荷物を出し入れするためには、駐車スペースに加えてある程度のゆとりが必要となります。
多くのコインパーキングでは、1台あたりの駐車マスを幅2.4m~2.5m×奥行き4.8m~5.0m(12.5㎡程度)としているのが一般的です。
これに加えて、車の出入りや転回のための車路、精算機や看板などの設備スペースを考慮する必要があります。
1台分の駐車場を設けるには、最低でも約9坪~10坪(約30㎡~33㎡)は必要とされますが、土地の形状やレイアウトによって必要な面積は異なります。
この程度の広さを確保することで利用者は隣の車を気にすることなくスムーズに乗り降りできるため駐車場の満足度向上につながるといえるでしょう。
長期的な視点で見れば、利用者の使いやすさを考慮した設計が安定経営の基盤となります。
【何坪必要?土地の広さ別】駐車可能な台数のシミュレーション

所有する土地で何台の車が駐車可能かを知ることは、事業計画を立てる上で非常に重要です。
駐車できる台数は、土地の総面積だけでなく、その形状や接道状況、車路をどのように配置するかによって大きく変わります。
ここでは、10坪から50坪以上まで、土地の広さ別に駐車可能な台数とレイアウトの目安をシミュレーション形式で紹介します。
自身の土地の条件と照らし合わせながら、具体的な駐車場のイメージを掴むための参考にしてください。
10坪~20坪の土地:車1~2台分のスペースが確保可能
10坪から20坪程度の土地では、駐車可能な台数が土地の形状やレイアウトによって変動します。例えば、10坪の土地では、普通車1台を駐車するのが一般的ですが、土地の形によっては軽自動車2台分の駐車スペースを確保できる可能性もあります。ただし、この場合、かなり窮屈になることがあります。20坪の土地であれば、駐車場のレイアウトによって異なりますが、普通車で2台から3台程度が目安とされており、レイアウトを工夫することで3台設置できる場合もあります。月極駐車場として活用する場合、4台程度の駐車が現実的とされることがあります。 この規模の駐車場では、場内に車路を設ける余裕がないことが多いため、前面道路に直接バックで入れたり、頭から入れて切り返して出たりするレイアウトが基本です。そのため、土地の間口が広いほど、車の出し入れがしやすくなります。都市部の狭小地などでも、月極駐車場として十分に活用できる広さです。
30坪の土地:車3~4台を配置できるレイアウト例
30坪の広さがあれば、駐車場のレイアウトの選択肢が広がります。
一般的には、3台から4台程度の駐車スペースを確保することが可能です。
例えば、前面道路に対して直角に駐車する一般的な並列レイアウトでは3台分をゆったりと配置することが可能です。
土地の形状が正方形に近く、間口と奥行きが十分にあれば、場内に簡易的な車路を設けて4台を配置することも検討できます。
ただし、4台にすると1台あたりのスペースや通路が狭くなり、利用者が使いにくさを感じる可能性も出てきます。そのため、無理に台数を増やすよりも、3台で広々とした使いやすい駐車場にする方が、結果的に稼働率が安定するケースもあります。
50坪以上の土地:車路を設けた効率的な配置が可能に
50坪以上の広さがある土地であれば、効率的で使いやすい駐車場の設計が可能です。 例えば、敷地内に専用の車路を設けることもできるでしょう。50坪の土地では、レイアウトや駐車場の種類にもよりますが、月極駐車場で8台程度、コインパーキングで7台程度の駐車スペースを確保できるのが一般的です。敷地の中央に車路を一本通し、その両側に駐車マスを配置する対面式のレイアウトなどが考えられます。 さらに70坪、100坪と広くなれば、収容台数も10台以上となり、大規模なコインパーキング経営も視野に入ってきます。多くの車両を収容できるため、高い収益性を見込むことが可能でしょう。土地のポテンシャルを最大限に引き出すレイアウトを専門家と相談しながら検討することが重要です。
変形地や狭小地でも駐車場経営は実現できる?
家を建てるには不向きな、いびつな形をした変形地や、面積の小さな狭小地であっても、駐車場経営であれば実現できる可能性は十分にあります。
例えば、三角形の土地や、道路から奥まった場所にある旗竿地などは、建物の建築には制約が多いですが、駐車スペースとしては活用できる場合があります。
たとえ1台分のスペースしか確保できなくても、そのエリアに駐車場の需要があれば、安定した収入源になり得ます。特に、周辺に駐車場が少ない住宅密集地や、駅に近い便利な立地であれば、建築を諦めた土地でも、駐車場として活用する価値があるといえるでしょう。
駐車場のレイアウトで変わる必要面積
駐車場経営において、土地の面積と同じくらい重要なのがレイアウトの設計です。
同じ広さの土地でも、駐車マスや車路の配置方法によって、収容できる台数や利用者の使い勝手は大きく異なります。
土地の形状や、道路にどのように接しているかといった条件を考慮し、最も効率的なレイアウトを選択することが収益最大化につながります。
ここでは、代表的な駐車形式である「並列駐車」と「縦列駐車」の特徴と、それぞれで必要となるスペースについて解説します。
並列駐車:一般的な駐車形式で必要なスペース
並列駐車は、複数の車を横に並べて駐車する最も一般的なレイアウトです。
スーパーや商業施設の駐車場でよく見られる形式で、各車両が通路に直接面しているため、他の車に影響されることなく自由に入出庫できるという大きなメリットがあります。
このレイアウトを成立させるためには、駐車スペースに加えて、車両が通行したり向きを変えたりするための車路が必要です。
この車路は、利用者が安全かつスムーズに通行できるよう、少なくとも5m以上の幅を確保することが推奨されます。
そのため、土地にはある程度の奥行きが求められますが、効率的に多くの車両を収容できるため、ほとんどの駐車場で採用されています。
縦列駐車:細長い土地を有効活用できる駐車形式
縦列駐車は、車両を前後に一列に並べて駐車する形式です。
このレイアウトの最大のメリットは、奥行きのある狭小地でも有効活用できる点です。
並列駐車のように広い車路を設ける必要がないため、限られたスペースを最大限に駐車エリアとして使えます。
しかし、奥に駐車した車を出すためには、手前にある車を一度移動させなければならないというデメリットがあります。
このため、不特定多数が利用するコインパーキングには不向きです。
主に家族や特定の法人など、利用者同士で車の移動を調整できる関係にある月極駐車場で採用されることが多いレイアウトです。
駐車場経営の種類で見る特徴と必要坪数

駐車場経営には、毎月固定の賃料を得る「月極駐車場」と、時間単位で料金を得る「コインパーキング」という主要な二つの種類があります。
また、狭い土地の収容台数を増やす方法として「機械式駐車場」も選択肢の一つです。
これらの経営方法は、それぞれ初期費用、収益性、適した立地条件、そして必要となる坪数が異なります。
自身の土地の状況や経営方針に合った種類を選ぶことが、成功への第一歩です。
ここでは、各種類の特徴と必要坪数の目安を見ていきます。
月極駐車場:少ない初期費用で始めたい人におすすめ
月極駐車場は、利用者と1ヶ月単位で契約を結び、毎月決まった賃料収入を得る経営方式です。
この方式の最大のメリットは、コインパーキングのような精算機やロック板といった高額な設備が不要なため、初期投資を大幅に抑えられる点にあります。
必要な整備は、土地の整地、区画のライン引き、車止めや看板の設置程度で済むことが多く、手軽に始められます。
そのため、車1台分のスペースである約4.5坪からでも十分に経営が可能です。
収益は契約台数に比例し、満車状態が続けば安定した収入が見込めますが、空き区画が出るとその分収入が減少します。
住宅街やオフィス街など、長期間にわたって駐車場を必要とする人が多いエリアに適しています。
コインパーキング:精算機などの設備スペースも考慮しよう
コインパーキングは、不特定多数の利用者に時間単位で駐車スペースを提供し、その利用時間に応じた料金を徴収する方式です。
駅前や繁華街、商業施設周辺など、人の流動が多く短時間駐車の需要が高い立地で高い収益性を発揮します。
運営には精算機、ロック板またはゲート、照明、看板などの設備が必須となり、月極駐車場に比べて初期費用は高額になる傾向があります。
また、これらの設備を設置するためのスペースも駐車マスとは別に必要となるため、ある程度の広さが求められるでしょう。
一般的に、コインパーキング経営に必要な最低限の土地面積は約9坪(30平方メートル)程度とされており、車両2台分の駐車スペースと精算機などの設置スペースを確保できる広さがあれば始められます。1台分の駐車スペースでも経営は可能ですが、収益性は土地の立地や稼働率、料金設定など多くの要素によって変動するため、土地の広さだけで採算性を判断することはできません。
一括借り上げ方式など初期費用を抑えて始められる運営方法もあり、稼働率次第では、月極駐車場を大きく上回る収益を上げることも可能です。
機械式駐車場:狭い土地で収容台数を最大化する方法
機械式駐車場は、昇降機やパレットを利用して車を上下二段や多段式、あるいはパズル式のように車を移動させて格納することで、限られた土地面積により多くの車を収容できるシステムです。
平面駐車場では数台しか駐車できないような狭い土地でも、空間を縦に活用することで収容台数を大幅に増やすことが可能になります。
このため、地価が非常に高い都心部の狭小地などで採用されることが多いです。
ただし、機械装置の導入には数百万円単位の多額の初期費用がかかるうえ、定期的な保守点検費用などのランニングコストも発生します。
また、入出庫に時間がかかる、大型車など車種に制限があるといった点も考慮する必要があるといえるでしょう。
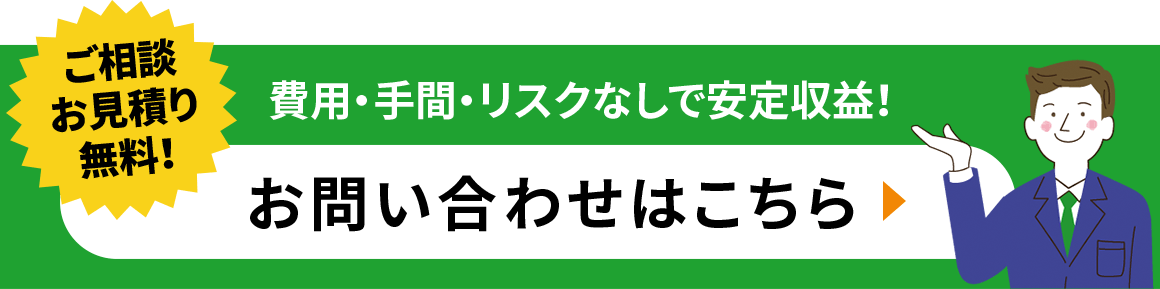
駐車場経営の収益はどれくらい?費用と収入モデルを紹介
駐車場経営を始めるにあたり、どの程度の収益が見込めるのかは最も関心の高い点です。
収益は、駐車料金、台数、そして稼働率によって決まりますが、そこから初期費用や税金、管理費などの経費を差し引いたものが実際の利益となります。
ここでは、駐車場経営に必要となる費用の具体的な内訳を明らかにし、土地の坪数や経営方式に応じた収入のシミュレーションを紹介します。
これにより、事業計画を立てる際の具体的な収支のイメージを掴むことが可能になるでしょう。
駐車場経営にかかる初期費用と維持費の内訳
駐車場経営にかかる費用は、事業開始時に必要な「初期費用」と、運営を続ける上で継続的に発生する「維持費」に分けられます。
初期費用の主なものは、土地の整地やアスファルト舗装、砂利敷きなどの工事費用です。
これに加えて、区画線を引く費用、車止めや看板の設置費用などがかかります。
コインパーキングの場合は、精算機、ロック板、照明、防犯カメラといった設備の購入・設置費用がさらに上乗せされます。
一方、維持費としては、毎年課税される固定資産税や都市計画税があります。
その他、場内を清潔に保つための清掃費、照明などの電気代、設備の保守点検費用、そして事故やトラブルに備えるための保険料などが定期的に必要です。
【坪数別】月極・コインパーキングの収益シミュレーション
駐車場の収益は、土地の広さや立地、経営方式によって大きく異なります。
例えば、月極駐車場の場合、東京23区で5台分の駐車場を経営すると、年間収入は約158万円になる可能性があります。ただし、郊外では1台あたりの月額料金が6,000円〜8,000円程度になることも多く、10台分の駐車場で年間収入が約72万円〜96万円が目安となるでしょう。
これらのシミュレーションは満車を想定しており、実際には経費も考慮する必要があります。
一方、コインパーキングの年間売上は、立地や稼働率、料金設定によって大きく変動します。
例えば、10時間稼働する5台のコインパーキングで、1台あたりの1日の売上が1,200円の場合、月間売上は約18万円、年間売上は約216万円になる可能性があります。
ただし、この売上はあくまで一例であり、実際の売上は立地や稼働状況によって大きく異なるため、周辺の競合駐車場の料金や入庫状況を調査し、適切な料金設定を行うことが重要です。
コインパーキングは月極駐車場に比べて初期費用や管理費が高くなる傾向があるため、売上だけでなく、初期費用やランニングコストを差し引いた純利益で比較することが重要です。
初心者でも安心!駐車場経営の始め方4ステップ
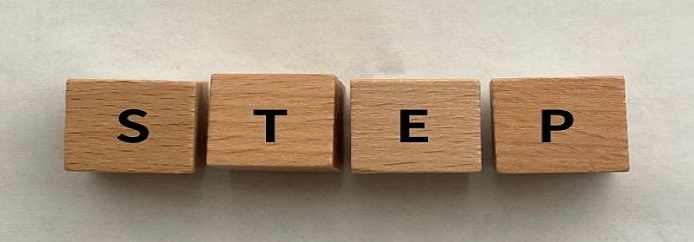
駐車場経営は、アパート経営など他の不動産投資と比較して、構造物が少ないため管理がしやすく、初心者でも参入しやすい土地活用方法です。
しかし、事業として成功させるためには、事前の準備と計画的な進行が欠かせません。
ここでは、駐車場経営を始めるための具体的な手順を4つのステップに分けて分かりやすく解説します。
この流れに沿って一つずつ進めることで、初めての方でも迷うことなく、スムーズに駐車場運営をスタートさせることが可能です。
Step1. 経営方式を決める(個人経営・管理委託・一括借り上げ)
駐車場経営を始めるにあたり、まずどのような方式で運営していくかを決定します。
選択肢は主に「個人経営」「管理委託方式」「一括借り上げ方式」の3つです。
個人経営は、全ての業務を自分で行うため収益性が最も高くなる可能性がありますが、手間と時間がかかります。
管理委託方式は、集金や清掃、トラブル対応といった日常の管理業務を専門の会社に手数料を支払って任せる方法で、運営の手間を軽減できます。
一括借り上げ方式は、駐車場会社に土地そのものを貸し出し、会社に駐車場運営の全てを任せる方法です。
土地の所有者は、駐車場の稼働状況に関わらず毎月一定の地代収入を得られるため、比較的リスクが低く安定した経営が可能です。
Step2. 信頼できるパートナー会社に相談し事業計画を立てる
経営方式の方向性が決まったら、複数の駐車場運営会社に相談し、比較検討することが重要です。
各社の実績、サポート内容、提示される条件などを吟味し、信頼できるパートナーを選びます。
選定した会社と共に、所有する土地の立地条件や周辺の市場環境を調査・分析し、具体的な事業計画を策定します。
この段階で、駐車場の最適なレイアウト、収容台数、料金設定などを決定します。
また、初期費用やランニングコスト、予想される収益を詳細に算出し、採算が取れるかどうかの収支シミュレーションを行います。
この計画の精度が、後の経営の安定性を左右します。
Step3. 土地の舗装や必要な設備の設置工事を実施する
事業計画が確定し、運営会社との契約が完了したら、駐車場の造成工事を開始します。
まず、土地を平らにならす整地作業から始めます。
その後、利用者の利便性や管理のしやすさを考慮して、砂利敷きやアスファルト、コンクリートなどで地面を舗装します。
舗装工事が終わると、駐車スペースを明確にするための区画線を白線で引き、各区画に車止めを設置します。
料金や利用案内を記載した看板の設置もこの段階で行います。
コインパーキングの場合は、これらに加えて精算機、ロック板、照明、防犯カメラといった運営に必要な各種設備を設置して、駐車場としての体裁を整えます。
工事期間は規模によりますが、数日から数週間が目安です。
Step4. 利用者の募集を開始し運営をスタートする
造成工事が完了し、駐車場としていつでも利用できる状態になったら、いよいよ運営のスタートです。
月極駐車場の場合、利用者の募集活動が必要となります。
現地の看板で募集を告知するほか、近隣の不動産会社に仲介を依頼したり、インターネットの駐車場検索サイトに情報を登録したりすることで、広く借り手を探します。
コインパーキングの場合、一括借り上げや管理委託であれば、運営会社が集客から運営管理までを行うのが一般的です。
オープン後は、定期的な場内の清掃や設備のメンテナンス、利用者からの問い合わせ対応などを行いながら、安定した稼働を目指します。
駐車場経営で失敗しないための3つの成功法則
駐車場経営は比較的始めやすい土地活用ですが、安易に始めると「利用者が全く集まらない」「収益が経費を下回ってしまう」といった失敗に陥ることもあります。
安定した収益を継続的に得ていくためには、事業開始前に押さえておくべき成功の法則があります。
ここでは、駐車場経営で失敗を回避し、事業を成功に導くために不可欠な3つの法則を解説します。
これらのポイントをしっかりと実践することで、経営リスクを低減し、収益の最大化を図ることが可能になります。
法則1. 土地の周辺環境やニーズを徹底的に調査する
駐車場経営の成功は、立地が9割と言っても過言ではありません。
事業を開始する前に、所有する土地の周辺環境を徹底的に調査し、駐車場の需要が本当にあるのかを見極めることが最も重要です。
駅や商業施設、病院、オフィスビルなどが近くにあるか、周辺に住宅は多いか、といった点を地図と現地調査で確認します。
また、競合となる他の駐車場の場所、料金、そしてどの程度利用されているか(稼働状況)を自分の目で確かめることも不可欠です。
こうした調査を通じて、月極駐車場の需要が高いのか、あるいは短時間利用のコインパーキングが適しているのかを判断し、需要に合った経営形態を選択します。
法則2. 稼働率を上げるために適切な料金設定を行う
駐車場の収益を最大化するためには、稼働率をいかに高めるかが鍵となり、そのためには適切な料金設定が不可欠です。
料金を決める際は、まず周辺にある競合駐車場の料金を徹底的に調査します。
その相場から大きく外れた高い料金設定では利用者に敬遠され、逆に安すぎると満車になっても十分な収益が得られません。
地域の需要動向に合わせて、平日と休日、昼間と夜間で料金を変えたり、長時間利用者向けに最大料金を設定したりするなど、柔軟な価格戦略も有効です。
オープン後も稼働状況を定期的にチェックし、利用者が少ないようであれば料金を見直すなど、常に最適化を図る姿勢が求められます。
法則3. 利用者が使いやすいように管理体制を整える
利用者が一度だけでなく、繰り返し使いたいと思える駐車場にすることが安定経営につながります。
そのためには、場内を常に清潔で安全な状態に保つことが基本です。
定期的に巡回してゴミ拾いや除草を行い、清潔感を維持します。
特に夜間の利用者のために、場内照明を十分に明るくして死角をなくしたり、防犯カメラを設置したりするなどの安全対策は、女性利用者などの安心感を高めます。
また、精算機の故障や出庫トラブルといった緊急時に、迅速に対応できる連絡先を分かりやすく表示しておくことも重要です。
こうした地道な管理が利用者の信頼を生み、リピート利用を促進します。
まとめ|土地の広さに合わせた駐車場経営で安定収益を目指そう!
駐車場経営は、狭小地や変形地などでも始めやすい土地活用方法として、多くの方に注目されています。
最低4.5坪(約15㎡)からスタートでき、土地の形状や経営方式に応じて収益性を高めていくことが可能です。
「何坪から始められるのか?」「何台駐車できるのか?」「どのくらいの収益が見込めるのか?」といった疑問も、正しい知識とシミュレーションを行えば、具体的な事業計画につなげることができます。
駐車場経営を成功させるためには、
• 周辺ニーズの把握
• 適切な料金設定
• 利用者に配慮したレイアウトと管理体制
が欠かせません。
まずは所有する土地の可能性を見極め、信頼できるパートナーと相談しながら、無理のない範囲から計画を立ててみてはいかがでしょうか。
小さな一歩が、安定収益への大きな一歩になるかもしれません。
土地活用をご検討の方は、ぜひユアー・パーキングまでお気軽にお問い合わせください。
ユアー・パーキングのサービスについて詳しくはこちらをご覧ください。
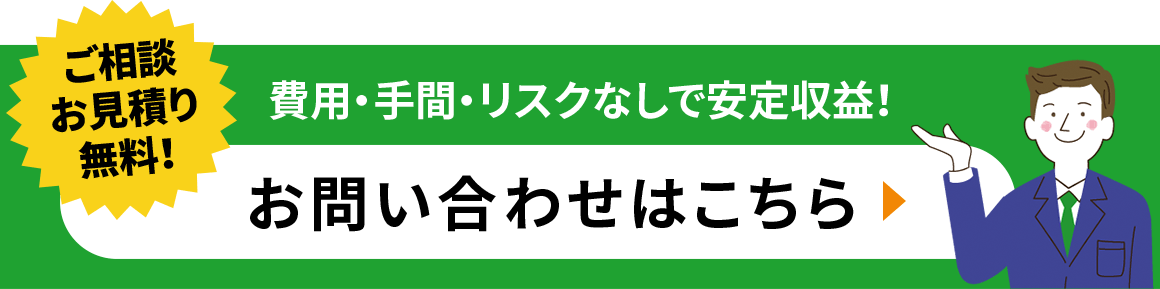
- HOME
- お役立ちコラム
- コインパーキングの経営
- 駐車場経営は何坪から?台数ごとの必要面積と収益の目安を解説