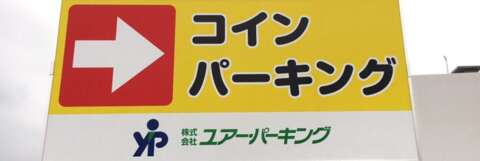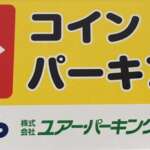- HOME
- お役立ちコラム
- コインパーキングの設備
- 駐車場の耐用年数を種類別に解説|国税庁の法定基準と減価償却
駐車場経営に必要な設備は法定耐用年数に応じて、減価償却することができます。
国税庁が定める法定耐用年数は、駐車場の構造や舗装、設備の種類によって細かく分類されています。
例えば、アスファルト舗装とコンクリート舗装では年数が異なり、立体駐車場も自走式か機械式かで扱いが変わります。
これらの耐用年数を正しく理解し、減価償却を行うことで節税につながります。本記事では種類別の法定耐用年数、減価償却について詳しく解説します。
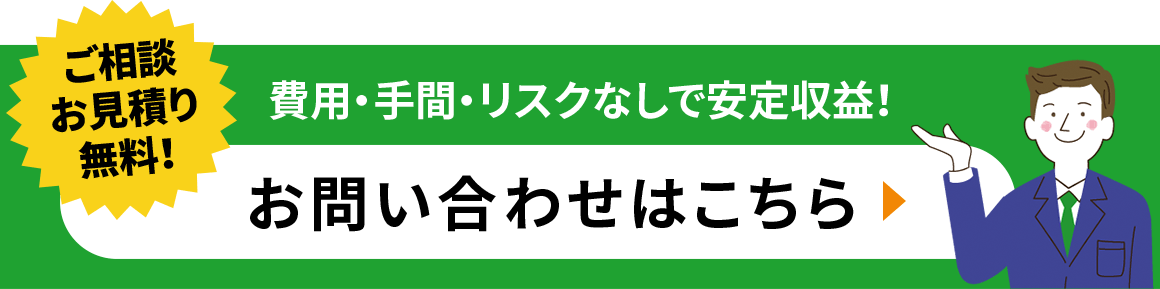
駐車場の耐用年数とは
耐用年数とは、税法上で定められた資産を使用できるとみなされる期間のことです。
耐用年数は、一般的な作業条件のもとで使用していくことや、メンテナンスを行うことを前提として年数が定められています。
国税庁が公表する耐用年数表に基づいて判断され、減価償却費を計算する際の基準となります。駐車場に関連する資産は、主に地面の舗装やフェンスなどの「構築物」と、機械式駐車場や精算機といった「機械及び装置」に分類されます。
それぞれの資産がどの区分に該当するかを正しく見極めて、会計処理を行うことが必要です。
減価償却の仕組みについて
減価償却とは、事業のために使用する建物や設備などの固定資産(償却資産)の取得にかかった費用を、数年間にわたって分割して費用計上する会計上の手続きです。
例えば、高額な駐車場設備を導入した場合、その費用を一度に計上するのではなく、法定耐用年数に応じて毎年少しずつ経費として計上します。
これにより、税金計算の基準となる所得金額を減らせるため、節税効果が得られます。
耐用年数が経過したらどうなるのか
法定耐用年数が経過しても、その駐車場設備が物理的に使用できなくなるわけではありません。
耐用年数はあくまで税法上の減価償却を行うための期間であり、実際の寿命とは異なります。耐用年数を過ぎるとその設備に対する減価償却は終了し、帳簿上の価値は備忘価額である1円となります。
しかし、平面駐車場や各種設備は、適切なメンテナンスを続けていればその後も問題なく使用し続けることが可能です。したがって、耐用年数経過後も事業用の資産として活用できます。
【構造・設備別】駐車場の法定耐用年数一覧

駐車場の法定耐用年数は、その構造や設備によって大きく異なります。
最も一般的なアスファルト舗装の駐車場から、コンクリート舗装、砂利敷き、さらには自走式や機械式の立体駐車場まで、それぞれに国税庁が定めた基準が存在します。
また、フェンスや看板、精算機といった付属設備にも個別の耐用年数が設定されています。ここでは、それぞれの種類に応じた具体的な法定耐用年数を一覧で確認していきます。
アスファルト舗装の駐車場
アスファルトで舗装された駐車場は、税法上「構築物」に分類され、「舗装道路及び舗装路面」の中の「アスファルト敷のもの」に該当します。
この場合の法定耐用年数は10年です。駐車場経営において最も一般的な形態の一つであり、比較的短期間で減価償却が完了します。
耐用年数15年であるコンクリート舗装と比較して、初期投資を早く費用化できる点が特徴です。
定期的なメンテナンスによって実際の寿命を延ばすことは可能ですが、税務上の計算ではこの10年という期間が基準となります。
コンクリート舗装の駐車場
コンクリートで舗装された駐車場は、アスファルト舗装と同様に構築物の舗装道路及び舗装路面に分類されますが、コンクリート敷のものとして扱われるため、法定耐用年数は15年です。
アスファルトよりも耐久性が高いことから、より長い耐用年数が設定されています。
初期費用は高くなる傾向にありますが、その分、長期間にわたって安定した利用が見込めます。簡易的な整地とは異なり、明確な構築物として資産計上され、15年かけて減価償却を行います。
砂利敷きの駐車場
土地を整地して砂利を敷いただけの駐車場も、構築物の舗装道路及び舗装路面に分類され、構築物のうち舗装道路及び舗装路面の石敷のものに該当します。法定耐用年数は、コンクリート舗装と同様に15年です。
ただし、駐車場にする前から砂利が敷いてあり、追加で砂利を足した場合は、維持管理・原状回復のために行うものであるとみなされ、修繕費として処理できます。また、少額減価償却資産の適用を考えると10万円以下でしたら修繕費か消耗品でよいことになります。
自走式立体駐車場(鉄骨造・RC造)
利用者が自ら運転して駐車する自走式立体駐車場は、税法上「建物」として扱われます。
その法定耐用年数は構造によって異なり、鉄骨造の場合は31年、一方で鉄筋コンクリート(RC)造の場合は38年です。これらは店舗用や車庫用など、建物の用途によって適用される耐用年数が定められています。
パレットなどを動かす機械式駐車場とは異なり、建物そのものの構造が評価されるため、非常に長い期間で減価償却を行うことになります。
機械式立体駐車場
車両をパレットなどに乗せて機械操作で移動・格納する機械式駐車場は、建物ではなく「機械及び装置」に分類されます。
そのため、自走式立体駐車場とは全く異なる耐用年数が適用されます。
どの区分に該当するかは設備の具体的な構造によりますが、一般的には「昇降機」として15年、あるいはエレベーターがない二段式や多段式のような装置は「その他のもの」として10年と判断されることが多いです。
認定駐車場として扱われる場合でも、税法上の分類は機械装置となります。
駐車場に設置される付属設備の耐用年数
駐車場経営においては、舗装や駆体といった主要な構造物だけでなく、それに付随する様々な設備も減価償却の対象となります。
例えば、敷地を囲うフェンスや外構、利用者を誘導する看板、夜間営業に必要な照明設備、料金を徴収する精算機やロック板などが挙げられます。
これらの付属設備は、駐車場本体とは別に、それぞれの種類に応じた法定耐用年数が定められています。
正確な資産管理と税務申告のためには、これらの設備を個別に把握し、適切な期間で償却処理を進める必要があります。
フェンスや外構
駐車場に設置されるフェンスや外構は、税法上「構築物」として扱われます。
その耐用年数は構造によって異なります。例えば金属製のフェンスであれば「金属造のもの」に該当し、法定耐用年数は10~15年です。
ブロック塀などの場合は30年が適用されることもあります。駐車スペースを区切るための簡易的なロープなどは、資産計上せず消耗品費として処理することも考えられます。
どのような構造で、どの程度の規模の設備かによって会計処理の判断が変わるため、設置時にはその内容を明確に記録しておくことが求められます。
看板や照明設備
駐車場の看板や照明設備も減価償却資産です。
看板は「構築物」の中の「看板及び広告設備」に分類され、金属製のものであれば20年、それ以外のものは10年といった耐用年数が適用されます。
一方、照明設備は「建物附属設備」の「電気設備(照明設備を含む)」に該当し、一般的に法定耐用年数は15年です。
これらの設備は駐車場運営に不可欠であり、取得価額を正しく把握し、それぞれの耐用年数に基づいて減価償却計算を行うことが必要です。
精算機やロック板
コインパーキングなどで使用される設備は、それぞれの性質に応じて個別に判断する必要があります。
例えば、精算機は、「機械及び装置」に分類され、法定耐用年数は5年です。一方、ロック板(フラップ板)、ゲート機なども「機械及び装置」に分類されますが、法定耐用年数は10年になります。
これは、どちらも「区分」は「機械及び装置」ですが、「資産の種類」が異なるため、法定耐用年数が異なるのです。
ただし、システム一体型(例:精算機+ゲート)の場合は、全体を「機械装置」として一括計上し、主たる部分(多くは精算機)の耐用年数で処理するケースもあります。
設備の性質に応じて適切に分類することが重要です。
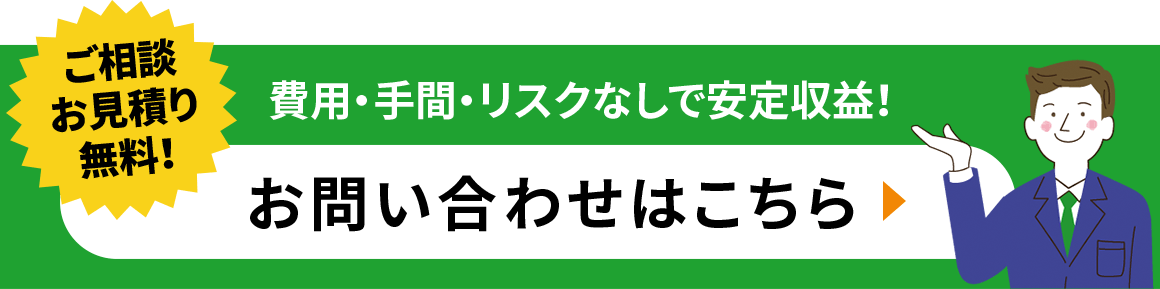
駐車場の減価償却費を計算する方法

減価償却の計算方法には主に「定額法」と「定率法」の2種類が存在します。選択する方法によって、経費の計上方法が異なります。それぞれの計算方法を見ていきましょう。
h3:毎年同じ額を償却する「定額法」
定額法は、固定資産の取得価額に定められた償却率をかけて減価償却費を計算する方法です。
この方法では、原則として毎年同額の減価償却費が計上されるため、計算が簡便で分かりやすいという特徴があります。資金計画や利益の見通しが立てやすく、安定した費用計上が可能です。
定額法の減価償却費 = 取得価額 × 定額法の償却率
例えば、アスファルト舗装(耐用年数10年)を50万円かけて行った場合の計算方法は、
・50万円 × 0.1 = 5万円 となります。
税法の改正により、建物や建物附属設備、構築物については原則として定額法で計算することが定められています。
したがって、アスファルト舗装やコンクリート舗装、フェンスなどの償却にはこの方法が用いられます。
初期の償却額が大きい「定率法」
定率法は、固定資産の未償却残高に、定められた償却率をかけて減価償却費を計算します。
この方法では、資産を取得した初年度の償却額が最も大きくなり、年数の経過とともに償却額が減少していきます。初期に多くの費用を計上できるため、事業開始時の利益を圧縮し、税負担を軽減する効果が期待できます。
定率法の減価償却費 = 取得価額 × 定率法の償却率
例えば、ゲート機(耐用年数10年)を50万円かけて購入した場合の計算方法は、
・1年目 50万円 × 0.205 = 102,500円
・2年目 (50万円 - 102,500円 )× 0.205 = 81,488円
・3年目以降も2年目と同様の計算方法となります。
機械式駐車場や精算機といった「機械及び装置」については、事前に税務署に届け出を行うことで定率法を選択することが可能です。
固定資産税(償却資産税)の申告
駐車場経営を行う上では、固定資産税(償却資産税)を申告する必要があります。
固定資産税は土地や家屋(立体駐車場など)、償却資産税は、土地・家屋以外の機材や設備にかかる税金のことで、その年の1月1日時点で固定資産を所有している場合に申告をしなければなりません。
なお、耐用年数を超過している資産についても申告の対象になります。減価償却を終えた資産でも、事業で使用している間は毎年申告する必要があります。
固定資産税は以下の式で算出できます。
固定資産の評価額(課税標準額)× 標準税率(1.4%)
固定資産税評価額は、毎年送付されてくる固定資産税納税通知書や、固定資産評価証明書を発行することで確認が可能です。
関連記事:駐車場の固定資産税は住宅用地の6倍なのか?計算方法や節税のポイントを紹介
耐用年数を延ばすために重要なメンテナンスのポイント
法定耐用年数は税務上の資産価値を算出するための期間ですが、駐車場の物理的な寿命は日々のメンテナンスによって大きく変わります。資産価値を維持し、長期にわたって安全で快適な駐車場を運営するためには、計画的な維持管理が必要です。
ここでは、耐用年数を伸ばすためのメンテナンスのポイントをご紹介します。
定期的な点検で劣化状況を把握する
駐車場の資産価値を維持し、長期的に活用するためには、定期的な点検が欠かせません。
専門業者による診断はもちろん、日常的な目視点検によっても、アスファルトのひび割れやへこみ、水たまりの発生、区画線の薄れ、照明設備の不点灯といった劣化の初期症状を発見できます。
これらの状況を定期的に記録・把握することで、どの部分にどのような対策が必要かを判断する材料となり、大規模なトラブルが発生する前に対処することが可能になります。点検は、計画的な修繕スケジュールを立てる上での第一歩です。
破損箇所は早めに修繕する
アスファルトの小さなひび割れや、機械式駐車場の部品のわずかな不具合など、軽微な破損を放置することは避けるべきです。
ひび割れから雨水が浸透すると内部の路盤が劣化し、最終的には大規模な舗装の打ち直しが必要になる可能性があります。また、設備の小さな故障が大きな事故につながる危険性もあります。
破損箇所を発見した際は、速やかに部分的な補修を行うことが重要です。早期の対応は、修繕費用を最小限に抑えるだけでなく、駐車場の安全性と利用者の信頼を確保することにもつながります。
適切な時期に大規模修繕を計画する
日々の細かな補修に加え、長期的な視点での大規模修繕計画も必要です。
例えば、アスファルト舗装は法定耐用年数である10年が一つの目安となりますが、交通量や立地条件、気候などによって劣化の進行度は異なります。
表面全体の摩耗やひび割れが目立ってきた段階で、オーバーレイ(既存舗装の上から新たな舗装を重ねる工法)や全面的な打ち替えといった大規模修繕を検討します。あらかじめ長期修繕計画を立て、必要な資金を積み立てておくことで、突発的な多額の出費に慌てることなく、計画的に資産価値の維持を図れます。
駐車場の耐用年数に関するよくある質問

駐車場の耐用年数や減価償却については、実際の経理処理において様々な疑問が生じることがあります。
例えば、駐車場の区画線(ライン)の扱いや、中古で駐車場設備を購入した場合の耐用年数の計算方法、さらには修繕費と資本的支出の判断基準など、実務に即した具体的なケースについての質問が多く寄せられます。
ここでは、そうした典型的な疑問点を取り上げ、それぞれの考え方や処理方法について解説します。
駐車場の区画線の耐用年数は何年ですか?
駐車場の区画線(ライン)の引き直し費用は、一般的に「修繕費」として扱われるため、特定の耐用年数は設定されません。
これは、ラインの引き直しが資産の価値を高める「資本的支出」ではなく、既存資産の機能を維持するための「原状回復費用」と見なされるためです。
したがって、支出した事業年度に一括で経費として計上します。ただし、駐車場を新設する際に、アスファルト舗装と同時に初めてラインを引く場合の費用は、舗装工事の取得価額に含めて「構築物」として減価償却の対象となります。
中古の駐車場設備を取得した場合の耐用年数はどうなりますか?
中古の駐車場設備を取得した場合、耐用年数は新品とは異なる計算方法を用います。
原則として、資産の法定耐用年数から既に使用された期間(経過年数)を差し引いた年数に、既に使用された期間(経過年数)の20%を加えた年数を耐用年数とします。計算式で表すと以下になります。
(法定耐用年数−経過年数)+(経過年数×0.2)
もし、法定耐用年数の全てが経過している資産を取得した場合は、法定耐用年数の20%に相当する年数が耐用年数となります。
資本的支出と修繕費の違いは何ですか?
資本的支出と修繕費は、どちらも資産の維持や改良に関わる支出ですが、税務上の扱いは大きく異なります。
修繕費は、資産の通常の維持管理や原状回復(例:ひび割れの補修、部品の交換)のための費用であり、支出した年度に全額を経費として計上できます。
一方、資本的支出は、資産の価値を増加させたり使用可能な期間を延長させたりする改良(例:駐車場の利用台数を増やす工事、新たな機能の追加)のための費用です。この場合、支出額は資産の取得価額に加算され、減価償却を通じて複数年度にわたって費用化されます。
まとめ
駐車場の耐用年数は、舗装の種類や設備の構造によって国税庁が定める法定耐用年数が適用されます。
アスファルト舗装は10年、コンクリート舗装は15年、自走式立体駐車場は建物の構造に応じて30年以上、機械式駐車場は装置として10年や15年が目安です。また、フェンスや精算機などの付属設備も個別の耐用年数で管理する必要があります。
これらの法定耐用年数に基づき減価償却を行うことで、資産の価値を正しく管理でき、節税や収支の安定化に繋がります。本記事で解説した内容を踏まえ、駐車場の耐用年数や減価償却を正しく理解し、駐車場経営を成功させましょう。
駐車場経営のことならユアー・パーキングにお任せください!
ユアー・パーキングにお任せいただければ、土地オーナー様は初期投資や維持管理などのコストや労力をかけることなく駐車場の運営が可能です。また、駐車場の利用状況に関係なく毎月一定の収入を得ることができます。
駐車場経営をご検討中の方は、ぜひ一度ユアー・パーキングにご相談ください。
ユアー・パーキングのサービスについて詳しくはこちらをご覧ください。
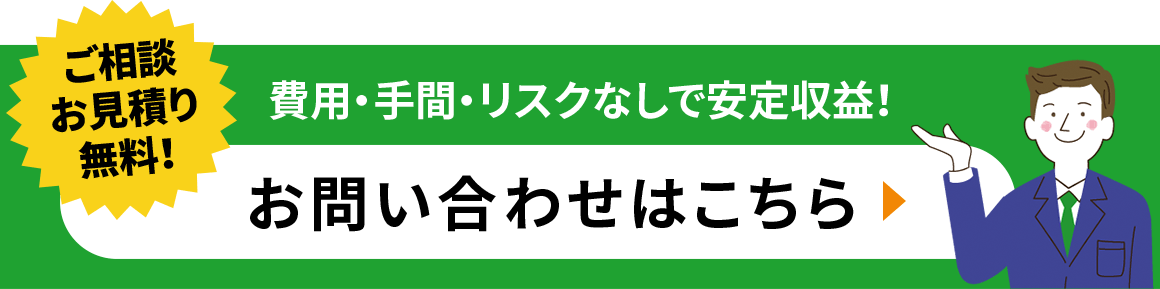
- HOME
- お役立ちコラム
- コインパーキングの設備
- 駐車場の耐用年数を種類別に解説|国税庁の法定基準と減価償却