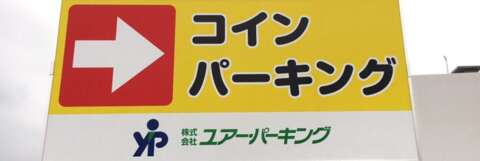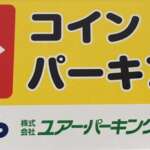- HOME
- お役立ちコラム
- コインパーキングの設備
- 駐車場経営に資格は必要?申請が必要となるケースも解説
駐車場経営を始める際、基本的に特別な資格は不要です。
駐車スペースや設備を整えれば誰でも資格不要で事業を開始する事ができます。
しかし、経営する駐車場の規模や種類によっては自治体への事前申請や届出が義務付けられる事があります。
こちらの記事では駐車場経営を始めるために知っておくべき情報、手続きを解説していきます。
ぜひ最後までお読みください。
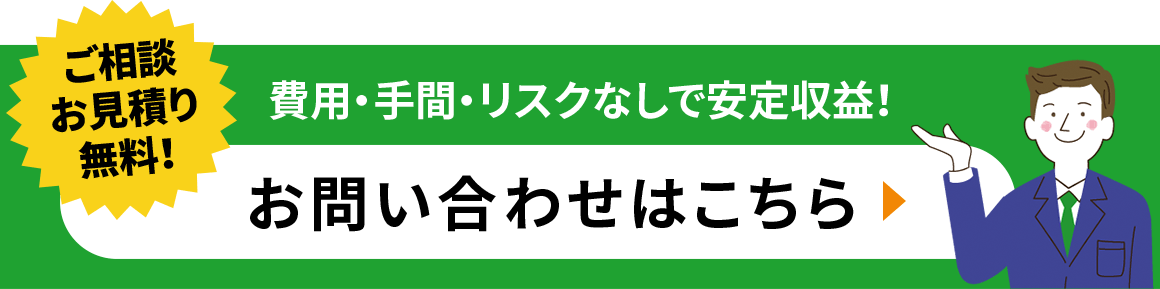
駐車場経営に資格は必要か
前途述べたように駐車場経営を始めるにあたって、特別な免許や資格は一般的には必要ありません。
土地を所有していれば資格がなくても誰でも手軽に経営がスタートできます。
しかし、免許や資格が不要だからといって無条件にすべての駐車場経営が許されるわけではありません。
駐車場経営で成功し、収益を得るために役立つ資格や知識について、次項で詳しく見ていきましょう。
駐車場経営で申請が必要なケースとは?
駐車場経営を行う際、申請が必要になるケースは主に土地の利用目的や設備の設置内容、駐車場の規模によって異なります。
例えば、駐車場の面積が一定の規模を超える場合、その土地の用途地域や周辺環境に応じて、都市計画法や建築基準法に基づいて行政への申請が求められることがあるのです。
自治体への申請が必要なのは「駐車場面積が500㎡以上」かつ「不特定多数の利用者から料金を徴収する」コインパーキングなどを
経営する場合です。
この場合、駐車場法の第11条・第12条に基づき、申請対象となり申請が必要になります。
一方で駐車場面積が500㎡に満たない場合や特定の契約者が利用する月極駐車場などの場合には届け出対象外となり申請は不要になります。月極駐車場であれば特別な設備を必要とせず比較的簡単に始められますが、コインパーキングのように機械を設置する場合には、
設備の安全性を確認するための検査や許可が必要になることがあります。
※ 「駐車場面積が 500㎡ 以上」とは、駐車場内の車路、設備、管理施設、附帯業務のための施設を含まない駐車桝だけの面積の合計をいいます。(例えば標準的な駐車桝である 5m×2.5mの場合では、40 台以上の場合届出が必要となります。)
管理規定者になる場合
前途のような駐車場面積500㎡以上のコインパーキングの“”駐車場管理者”になった場合も、自治体への届出が必要です。
この場合、駐車場の使用を開始してから10日以内に、「駐車場の名称」「運営者の氏名と住所」「使用時間」「駐車料金」などを定めた
管理規定の届出を行います。
この手続きを行うことで、自治体が駐車場の安全性や運営状況を把握し適切な管理が行われているかを確認します。
駐車場経営のための申請完了までの流れ
ここからは駐車場面積500㎡を超える駐車場を経営するために、あらかじめ自治体へ申請する方法の流れについてご説明します。

①必要書類を提出する
駐車場経営を始める際は、まず自治体に必要書類を提出します。
【駐車場面積が500平方メートルを超えた場合に必要な提出書類】
・路外駐車場設置届出書
・駐車施設の概要書
・平面式の場合は平面図
・駐車場の位置を表記したもの
・管理規程届
・委託する場合のみ業務委託契約書のコピー
提出する書類は、駐車場の規模や種類に応じて異なるため、事前に地元の市役所や区役所、もしくは自治体の公式ウェブサイトで内容を
確認することが大切です。
書類の種類には、駐車場設置に関する届出や管理規程などが含まれます。万が一、不明点があれば電話で問い合わせて正確な情報を得るとよいでしょう。
②書類審査を行う
駐車場設置申請における書類審査では、提出された申請書や必要書類が詳細に確認されます。
具体的には、駐車場の位置や面積、設備の配置、安全対策の計画などが法令や規則に適合しているかが重点的にチェックされます。
審査の際には、管轄する自治体の担当窓口だけでなく、都道府県警察の交通部門へも照会が行われます。警察は交通規制の観点から駐車場の出入口の位置や交通の流れ、安全確保に問題がないかを現地で調査します。
通常、書類提出から審査および警察による現地調査の完了までには約1か月を要します。
この期間は、書類の内容に不備があった場合の修正連絡や追加資料の提出対応も含まれるため、余裕をもって申請することが重要です。
③現地確認を行う
現地確認は、申請した駐車場の計画が実際の土地状況と一致しているかどうかを判断する重要なステップです。自治体の担当者は、
経営者の立会いのもとで現地を訪れ、申請時に提出された図面や書類と現場の状況に相違がないかを詳細に確認します。
もしここで土地の地形や樹木の配置、設備の設置状況に違いが見つかった場合は、その場で指摘されるか後日修正の指示が出されることがあります。
この確認作業において問題点が速やかに対応できないと、申請の承認が遅れ駐車場経営の開始が遅延するリスクにつながりますのでその際の対応をシミュレーションするなど不備があれば即座に行動できるようにしましょう。
④提出書類が返却される
現地調査が完了すると、申請した書類が自治体から返却されます。
この段階では、提出されたものに対して内容の確認や修正指示が含まれることがあります。
返却された書類に不備や修正点があれば、速やかに対応することが重要です。
一方で、問題がなければ、一定期間内に審査が終わり、許可証や認可書が交付されます。
この許可書が発行されるまでには通常、申請からおよそ1ヶ月から40日前後の時間を見込む必要がありますのでこれらの手続きを考慮して余裕を持ったスケジュールを立てることが求められます。
なお、こちらでご紹介した手続きの流れはあくまでも一般的なものです。
各自治体により返却の時期や手続きの流れに違いがあるため、申請時には必ず担当窓口に確認し最新の対応方法を把握しておくとよいでしょう。
駐車場経営を行う上で知っておくべきルールと注意点
いくつかの注意点と基本的なルールを理解すると駐車場経営を成功させることができるでしょう。
ここでは駐車場設置場所、形式に関する重要なポイントを解説します。
市街化調整区域では開発許可が必要になるケースがある
市街化調整区域において駐車場経営を行う際、開発許可が必要となる場合が複数あります。市街化調整区域は都市計画法で定められた区域であり、原則として都市の無秩序な拡大を防ぐため、住宅や商業施設の建築が制限されています。
駐車場を市街化調整区域内に設置する場合、一般的に建物の建設を伴わないため開発許可は不要とされますが、一定の条件を満たす場合には例外となることがあります。
敷地の区画を変更する際や、土地の形質を大幅に変更する場合、さらには土地の用途を変更する場合などには道府県知事や政令指定都市の長からの許可を取得する必要があります。
農地を駐車場にする際は農地転用の許可または届出が必要
農地転用とは、農地法に基づき農地を農地以外の用途に変更することを指します。
農地を駐車場に転用する際には、都道府県知事の許可を得る必要があります。
一方、市街化区域にある農地を転用する場合は、より簡易な手続きである「届出」を農業委員会に行うだけで転用が可能です。
出入口の設置には一定の制限がある
駐車場の出入口設置には、法律や技術基準による明確な制限が設けられています。特に500㎡以上の大規模な駐車場の場合、交通の安全を確保する観点から位置の制約が厳しくなるため、適切な設置場所を選定する必要があります。
たとえば、角地にある駐車場では、交差点の角から5メートル以内に出入口を設置できません。
これは出入口が交差点に近すぎると、車両の視認性が悪くなり、右左折する車両の動きを妨げて事故の原因となりやすいためです。
また、歩行者の通行場所である横断歩道近くに設置する場合も、横断歩道から最低5メートル離すことが義務付けられています。
この距離確保は歩行者の安全を守るだけでなく、出入口からの車両の発進や停止に要するスペースを確保するためにも重要です。
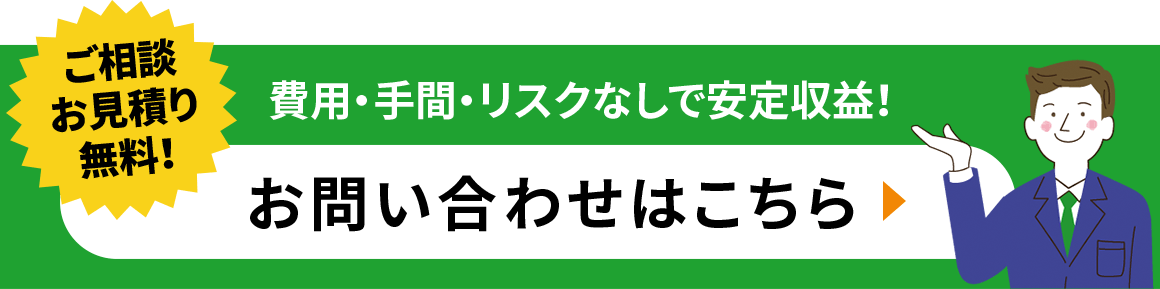
駐車場経営で役に立つ知識と資格とは?
駐車場を経営するのに特別な資格は必要ありませんが、
関連する資格や知識があればより安心して駐車場経営を進めることができるでしょう。
ここからは役立つ知識や資格についてご紹介します。
・日商簿記検定2級
日商簿記検定2級は、企業の経理や財務管理に必要な知識を体系的に学べる資格であり、駐車場経営にも大いに役立つ資格といえます。
駐車場経営には初期投資や運営コストを適切に把握し、収益性を確保するやり方が重要でありここで簿記資格があると、
個人で駐車場を経営する際も現状の経営状況を把握しコスト管理や利益の把握もでき、収益の流れを分析しやすくなります。
駐車場経営で役立つ知識の分野
資格取得に加え、駐車場経営には役立つ知識を学んでおくことも非常に重要です。
・車に関する法律の知識
車に関する法律の知識は、駐車場経営を円滑に進めるために欠かせません。
まず、道路交通法に基づき、駐車場の出入口や車両の通行に関する規制を理解しておくことが重要です。
これにより、安全で適法な運営が可能となります。さらに、自動車関連の法律は地域によって異なる場合があるため、該当する地方自治体の条例にも注意を払う必要があります。加えて、駐車場内で発生しうる事故やトラブルに対応するため、運営者としての責任範囲を把握し、適切な対策や保険加入を検討すべきです。こうした法律知識を備えることで、違反リスクを減らし、利用者に安心感を提供できる環境を整備していくことが求められます。
・税務に関する知識
駐車場経営に伴う税務知識は安定した収益確保に欠かせません。
税金に関する理解も必要になるでしょう。
例えば、“固定資産税”や“都市計画”は駐車場用地にかかる税金であり、毎年適切に納付する義務があります。駐車場の収入は“不動産所得”として扱われるため、確定申告の際には適切に経費を計上し、いくら税金がかかるのか節税対策を講じることも大切です。
こちらの4種類がおもに駐車場経営に関わる税金となります。
・固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日時点に不動産や土地を所有していると発生する税金です。
市町村が固定資産税評価額をもとに税額を算出し、納税者には毎年4月頃に納税通知書が届きます。
税率は1.4%です。なお、宅地などの場合は税額の減免がありますが、駐車場は更地評価となり、減免されることもありません。
・都市計画税
都市計画税は、固定資産税と同じく毎年1月1日時点で不動産や土地を所有していると発生する税金です。
毎年4月頃に固定資産税と併せて通知が届きます。上限0.3%の制限税率で、自治体によって異なるため確認しておくと良いでしょう。
・消費税
消費税は、商品やサービスを購入した際に、その対価の10%または8%を消費者が負担する税金です。
事業者は受け取った消費税を国や地方に納める義務があります。
土地の賃貸などの場合は非課税取引となりますが、駐車場経営では駐車場としてサービスを提供することとなるため、消費税が発生します。なお、個人事業主の場合は、一昨年もしくは昨年の上半期の課税売上高が1000万円を超える場合や適格請求書発行事業者に登録している場合には消費税を納税する義務がありますが、1000万円以下の場合、納税義務はありません。
・所得税
所得税は、年間所得から必要経費を差し引いた金額に掛けられる税金です。
駐車場経営で得た所得はおおむね不動産所得に該当し、駐車場経営のほかに給与所得などがある場合は確定申告が必要となります。
・リスク管理の知識
駐車場経営では、さまざまなリスクを把握して適切に対応することが重要です。
施設の老朽化や設備の故障、利用者とのトラブルといった問題が経営に影響を及ぼす可能性があります。
これらのリスクに対して予防策を講じるとともに、万が一の事態に備えた保険の活用も欠かせません。
また、法令や条例の改正に常に注意を払い、適切な手続きや対応を行うことが求められます。
周辺環境の変化や需要の変動もリスクとして考慮し、柔軟な経営計画を立てることが成功につながります。
リスク管理を徹底することで、安定した運営と長期的な収益確保が実現します。
最後に安心して駐車場契約を始めるための手順
駐車場契約を安心して始めるためのステップとしてここでは土地の活用相談から施工、
そして実際の利用開始までの基本的な手順について解説します。
土地活用のご相談
土地活用の相談は、駐車場経営を成功させるための重要な第一歩です。
土地の形状や広さ、アクセス状況、周辺の需要状況は多様で、それぞれの条件によって最適な活用方法が変わります。
例えば、駅周辺の利便性の高い場所では短時間利用が多いコインパーキングが適している場合があります。
一方で、住宅街近くの落ち着いたエリアでは安定した収益が見込める月極駐車場が選ばれやすい傾向があります。
相談の際には専門家が法規制の確認や、収益の見込み、初期投資の内容まで詳しく説明します。
実際にあるケースでは、土地の形状が細長いために駐車台数を確保しにくい場合、駐輪場やカーシェアリングの導入を提案することもあります。加えて、地元自治体の条例や都市計画による制限も調査し、違反なく運営できるかを見極めることが不可欠です。
このように、専門家と連携しながら土地の特性を正確に把握し、最適な活用プランを立てることで駐車場経営を効率的かつ収益性の高いものにできます。まずは信頼できる相談機関にアポイントを取り、さまざまなメリットデメリットを把握し具体的な話を進めることが成功の鍵を握るでしょう。
ご契約
駐車場経営を始めるにあたり、ご契約は非常に重要なステップとなります。
まず、プランの詳細や運営体制が確定した後、関係各社との契約内容を綿密に確認しましょう。
契約書には、初期投資額や維持管理費用、売上の分配方法、期間や解約条件などが明記されています。
「個人経営」や「管理委託方式」を選んだ場合は清掃、トラブル対応まで一括して行う必要があり、
経営の自由度が高い一方で手間も増えるでしょう。
一方、運営会社に一括で貸し出す場合は、月額賃料が保証されるため収益の安定性が確保できますが、
運営の詳細は委託先に任せる形となり、自己判断の余地は狭まるでしょう。
このように、経営の形態に応じて契約内容が異なるため自分に合った形態を慎重に選ぶことが重要となります。
施工
施工は駐車場経営の重要な工程であり、設計図に基づいた具体的な工事が進められます。
土地の形状や環境に合わせて、使い勝手の良い駐車スペースの配置や通路の確保が求められ、特に安全面では道路交通法などの関連法規を遵守し、出入口の位置や幅員に注意して設置します。
最終的に問題のない状態で利用開始へと移行します。
利用開始
駐車場の施工が完了し準備が整ったら、いよいよ利用開始に向けての具体的な段取りを進めます。
まずは駐車場の利用者にとって分かりやすく使いやすい環境を整えることが重要です。
例えば、駐車場の入口や出口に料金表示や利用ルールを明確に示した看板を設置し、利用者が迷わずスムーズに利用できるよう配慮します。こうした視覚的な案内は、初めて訪れる人でも安心して駐車できる環境づくりに欠かせません
これらの準備や運用開始後の改善活動を丁寧に行うことで、利用者満足度を高め、安定した収益を確保することが可能となります。
初期段階からきめ細かい運営体制を整え、長期的な駐車場経営の成功に結び付けることができます。
駐車場経営に関してのご相談はお気軽にユアー・パーキングまで!
駐車場経営に関する疑問やお悩みは、ぜひ一度経験豊富なユアー・パーキングへご相談ください!
土地の有効活用方法や運営上のポイントなど、初めての方でも安心してご相談いただける体制が整っております。
豊富な実績をもとに、皆さまの駐車場経営をしっかりと支援いたしますのでユアー・パーキングの専門サポートで、失敗しない駐車場経営を実現しましょう。
ユアー・パーキングのサービスについて詳しくはこちらをご覧ください。
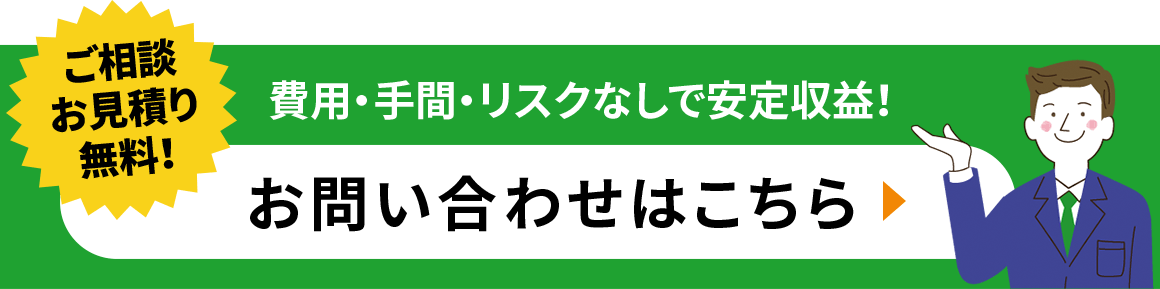
- HOME
- お役立ちコラム
- コインパーキングの設備
- 駐車場経営に資格は必要?申請が必要となるケースも解説